今年の国語の入試問題 は、「わかる」とはどういうことかがわかる文章です。
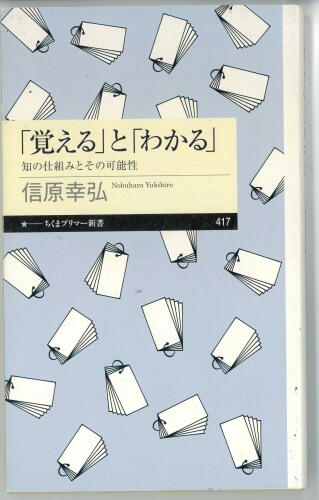
今年の国語の問題については、何よりも論説文の内容が大変興味深いものでした。
題材は、信原幸弘『「覚える」と「わかる」知の仕組みとその可能性』(ちくまプリーマー新書)
筆者は東大名誉教授で哲学の先生ですが、文章はとても平易で読みやすい文章です。
教師必読の内容なので、早速入手して読みました。
勉強というのは、ていねいに順序だてて教えれば出来るようになると、一般に考えられています。
塾の宣伝でも、「1対1」とか「つきっきり」とか、「お子様にぴったりの先生」などと言ったフレーズが飛び交います。
でも、実際指導してみると、何度も、同じことを何度も間違う生徒は少なくありません。。
私たちは経験上、力を受けるには、教えるだけでなく、繰り返し練習させる必要があると考えていますが、
信原先生は、まさに、そのことを主張されています。
試験に出た部分を紹介しますと、
「たとえば、数学の証明問題を考えてみよう。(中略)
証明問題を解くというのは、ようするにどの規則をどの順に適用するかを発見することだと言っていい。
しかし、たんにどの規則をどの順に適用するかがわかっただけでは、じつは証明が本当にわかったとは言えない。
たとえば、頭をひねってもなかなか証明問題が解けないので、ついつい答えを見てしまうことがある。」
しかし、答えを見ても、どうも「わかった」気にならないとして、
「答えを見れば、どの規則をどの順に適用して、前提から結論が導かれているかは「わかる」のだが、それでもどうも腑に落ちないのである。」
証明の流れを言われれば、そうなのか、と思っても、なかなか納得できないのです。
でも、すぐに出来るようになる生徒もいます。
それは、なぜでしょうか。
ていねいに教えてもらったからではありません。
信原先生はこう述べています。
「しかし、最初は腑に落ちなくても、証明を何度もたどりかえして、証明の流れに慣れてくると、やがて「あっ、わかった」と感じられる瞬間が訪れてこよう。
それは一証明のいわば「核心」が直観的に把握された瞬間である。
証明の本当の理解には、証明の核心を直観的につかむことが必要なのである。」
つまり、「わかる」とは、直感的に全体像がつかめるということなのです。
そうなるためには、
「最初は腑に落ちなくても、証明を何度もたどりかえして、証明の流れに慣れてくる」
ことが必要なわけです。
要するに、繰り返し練習をすること、まさに私たちが実践していることです。
ネットの発達で知らないことでも、検索すればすぐ調べられる便利な世の中になりました。
それを理由に、いろんな知識を覚える必要がなくなった、といった考えも出てきましたが、
信原先生のこの本には、「覚える」ことの意味とその重要性も書いています。
次回、一部を紹介しましょう。