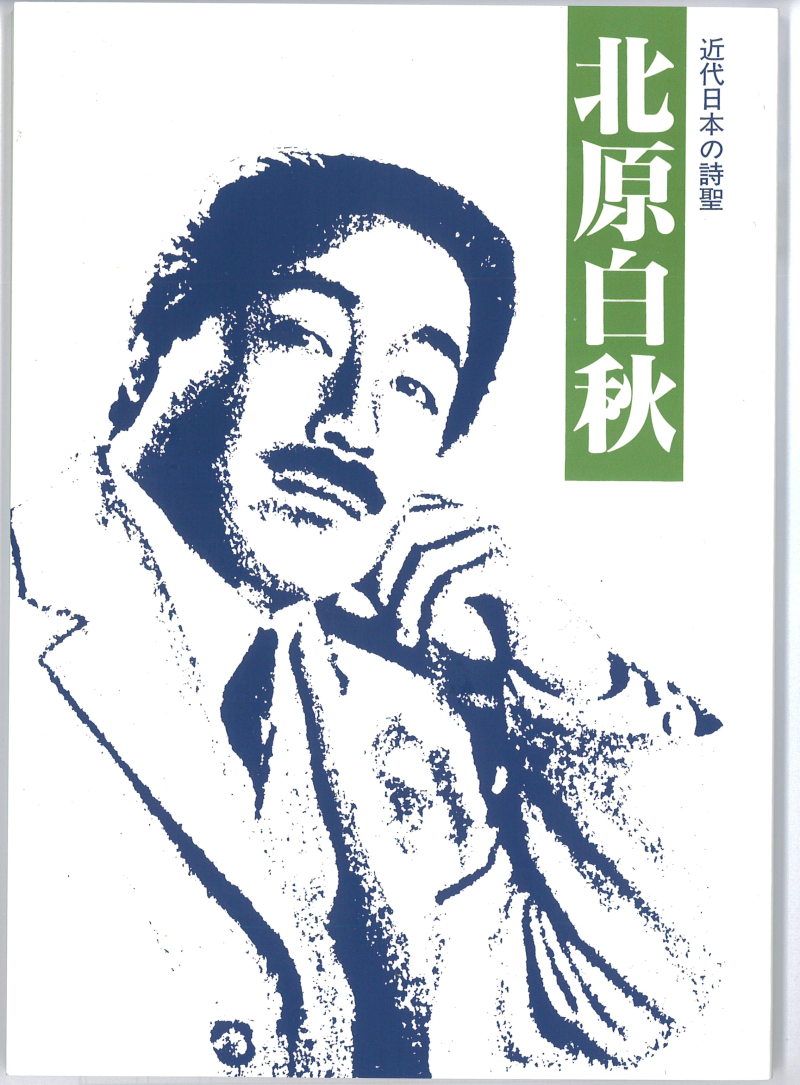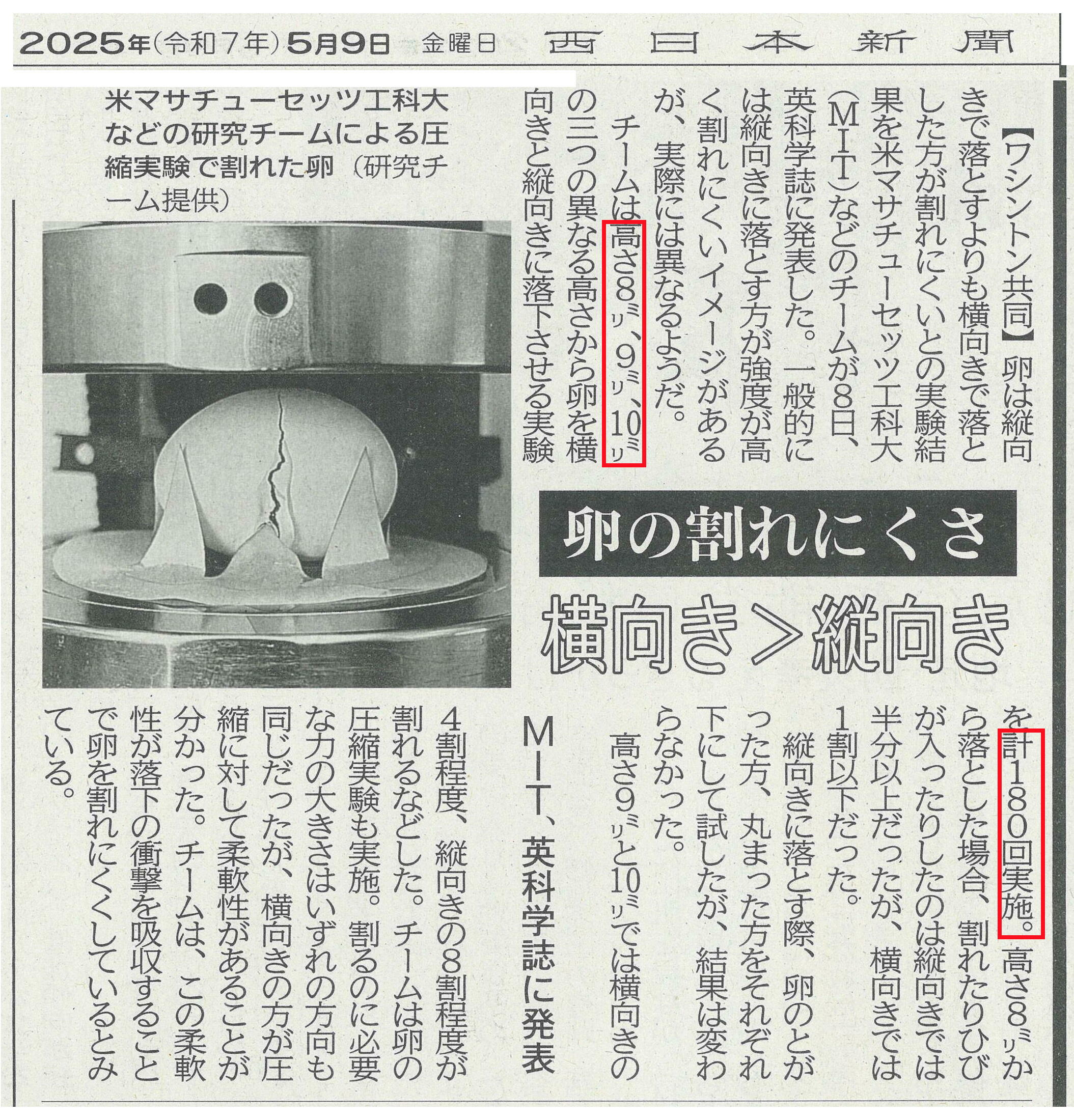もう藤ですね。
コロナの時は、人が集まらないように、咲く前に切られていました。
「そんなこともありましたね。」言ってるみたいです。
自然ってありがたい。

先日、卒業生のお母さんがあいさつに来てくれました。
この生徒は、なかなか勉強への意欲が持てなかったため
小学校から通っていた大手塾から転塾してきた子です。
私たちの指導は、生徒の間違った書き方を指摘し、出来たらほめる、というやり方です。
当たり前のようですが、授業形式だと生徒がどんな書き方をしているか、先生からは見えません。(見ません)
アルバイトの学生には、一対一でも、教えることが精いっぱいで、間違いを改めさせる「指導力」は無理です。
学校でも、ほとんどの先生たちは、ちゃんと教えているはずですが、
生徒のノートに(つまり、脳に)、そのまま反映されている保証はなく、
むしろ、間違ったことを書いている場合が少なくないのです。
ですから私たちは、生徒がノートにどう書いているをしっかり見ます。
でなければ、成績を上げるのは難しいからです。
そんな勉強を続けることで、勉強から逃げていた彼も、自分から積極的に取り組むようになりました。
残念ながら、ここで公開はできませんが、
本人から、と渡された、カードには、高校の部活で活躍している写真に、感謝の言葉と
「前向きに勉強できるようになりました。」
とのうれしいメッセージが書かれていました。
生徒一人ひとりが成長する姿を、進行形で見守ことができるのは、
何物にも代えがたい塾の仕事の醍醐味です。